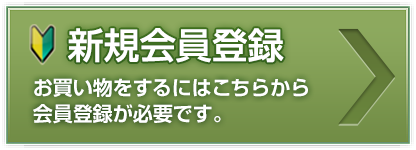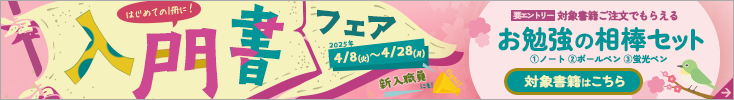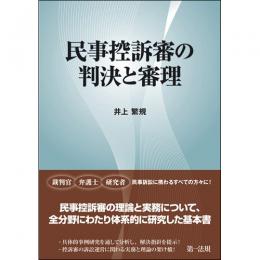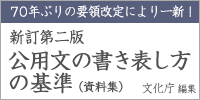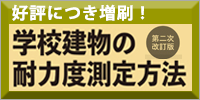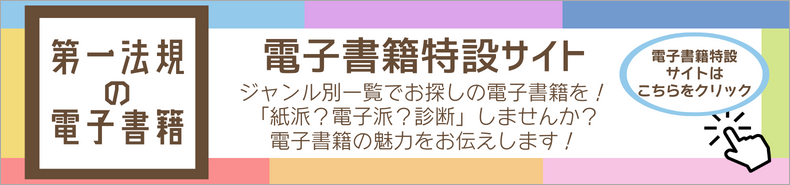//民事控訴審の理論と実務について体系的に研究した基本書//
3,981円 (本体:3,619円)

| ISBN |
978-4-474-02360-4 |
| 発刊年月日 |
2009-03-30
|
| 判型 |
A5判 |
| ページ数 |
474 |
| 巻数/略称 |
/ 民事控訴審 |
| 商品コード |
023606
|
民事訴訟の審理と判決のあり方について、これまでの理論、個別研究、実務事例を集大成し、新たな提言をまとめた書。2011年2月刊行の第4刷<補正版>において、第1編第3章第3節に「8 第1審判決の訂正」を新たに加え、また、最近の判例を追加するなどして、内容の充実と最新化を行った。
目 次
第1編 民事控訴審の判決書 1
■第1章 控訴の意義、要件及び効力 3
◎第1節 控訴の意義と控訴審の構造 4
1 控訴の意義 4
2 控訴審の構造 4
◎第2節 控訴の要件 4
1 第1審判決が控訴の許される終局判決であること 4
2 控訴の提起が適式かつ有効であること 5
3 控訴期間内に提起された控訴であること 6
4 控訴の利益が存在すること 7
◎第3節 控訴の効力 15
1 確定遮断の効力 15
2 移審の効力 15
3 控訴不可分の原則 16
◎第4節 控訴の取下げ 22
1 意 義 22
2 控訴の取下げの要件 23
3 控訴の取下げの方式 27
4 控訴の取下げの効果 28
5 控訴の取下げの擬制 29
6 控訴の取下げの合意 29
◎第5節 控訴権の放棄と不控訴の合意 30
1 意 義 30
2 控訴権の放棄の要件 30
3 控訴権の放棄の方式 32
4 控訴権の放棄の効果 33
5 不控訴の合意 34
◎第6節 控訴審の審理 35
1 続審制 35
2 訴訟手続 35
3 適法な控訴の提起 36
4 審判の対象 37
5 控訴審の口頭弁論 37
■第2章 事件番号、事件名及び当事者 39
◎第1節 事件番号・事件名の表示 40
1 事件番号・事件名の表示方法 40
2 事件番号・事件名の表示の例示 40
◎第2節 住所の表示 41
1 基本的な例示 41
2 人事訴訟事件の例示 42
3 法人に対する公示送達の例示 42
◎第3節 氏名の表示 42
1 一方から控訴が提起された場合 42
2 双方控訴の場合 42
3 控訴審において反訴が提起された場合 43
4 第1審の口頭弁論終結後に一般承継があった場合 43
5 補助参加人が控訴を提起した場合 43
6 附帯控訴がされた場合 43
7 控訴審における脱退の場合 44
8 選定当事者の場合 44
9 旧姓、旧名、旧商号の場合 44
10 死亡当事者の訴訟承継人の場合 44
11 破産管財人、更生管財人が当事者の場合 45
12 遺言執行者の場合 45
◎第4節 法定代理人の表示 45
1 一般的な場合 45
2 法人及び社団等 46
3 特別代理人 46
4 不在者 46
5 相続財産法人 46
6 法定代理人の変更 47
◎第5節 訴訟代理人の表示 47
1 弁護士 47
2 弁護士の復代理人 48
3 支配人 48
4 船 長 48
5 指定代理人 48
6 参 事 48
7 訴訟代理人の変更 48
■第3章 判決主文 51
◎第1節 訴訟判決の主文 52
1 不適法な控訴 52
2 第1審の訴え却下判決に対する適法な控訴の場合の取扱い 54
◎第2節 本案判決の主文 55
1 控訴棄却判決の主文 55
2 控訴認容判決の主文(その1・差戻判決) 57
3 控訴認容判決の主文(その2・自判) 67
4 控訴審において訴えの変更がされた場合の判決主文 97
5 特殊な訴訟形態における判決主文 151
6 特殊な判決主文 191
◎第3節 第1審判決の更正 223
1 更正の要件 223
2 更正決定をする裁判所 225
3 更正決定の手続 227
4 更正決定の効力 227
5 更正決定に対する不服申立て 227
6 更正決定が許される場合の例示 228
7 主文例と理由例 230
◎第4節 訴訟費用に関する主文 232
1 控訴棄却判決の場合 232
2 控訴の全部に理由がある場合 236
3 控訴の一部に理由がある場合 236
4 附帯控訴がされた場合の主文例 237
5 控訴審で訴えの変更がされた場合の主文例 238
6 訴訟承継があった場合 249
7 共同訴訟の場合 251
8 選定当事者の場合の主文例 252
9 当事者以外の第三者に負担させる場合 256
10 破棄差戻し後の審理の場合の主文例 257
◎第5節 仮執行宣言に関する主文 258
1 仮執行宣言のみに対する上訴の許否 258
2 控訴審における仮執行宣言(民訴法294条) 259
3 仮執行宣言のない請求認容の第1審判決につき、
控訴棄却判決において仮執行宣言を付する場合 261
4 原判決取消し・請求認容判決において仮執行宣言を
付する場合 263
5 仮執行宣言又は本案判決の変更による仮執行宣言の失効 263
6 仮執行宣言の失効の効果 265
7 仮執行宣言付き第1審判決後に弁済がされた場合の審理 278
■第4章 破棄差戻し後の控訴審の審判 281
◎第1節 原判決の破棄と事件の差戻し 282
1 原判決の破棄 282
2 全部破棄と一部破棄 282
3 事件の差戻し 283
◎第2節 破棄判決の拘束力 284
1 拘束力の根拠 284
2 拘束力の法的性質 285
3 拘束力の範囲 286
◎第3節 差戻し後の審理 291
1 新たな口頭弁論 291
2 訴訟代理権の復活 293
3 差戻し後の審判の範囲 293
◎第4節 原判決に関与した裁判官の関与禁止 296
1 上告審の破棄差戻判決による差戻審の場合 296
2 控訴審の取消差戻判決による差戻審の場合 297
◎第5節 差戻し後の判決 297
1 主たる主文 297
2 訴訟費用に関する主文 298
3 差戻し前の控訴審判決の引用の可否 299
第2編 民事控訴審の審理 301
■第1章 総 論 303
◎第1節 控訴審における訴訟運営の基本的視点 304
1 続審制の下における事後審的訴訟運営 304
2 控訴審における審理の焦点 304
3 続審制の原則 305
4 事後審的審理 305
5 民事控訴審の訴訟運営 306
◎第2節 控訴審における審理の実情 307
1 新受件数の推移 307
2 既済件数及び未済件数の推移 307
3 既済事件の審理期間 307
4 既済事件の口頭弁論期日の実施回数 308
5 既済事件の終局区分 309
6 既済事件の上告率 311
7 民事控訴審の審理の課題 311
◎第3節 民事控訴審における審理の問題点の改善方策 312
1 第1回結審について 312
2 人証の取調べの制限について 316
3 和解勧告について 318
4 控訴審判決書について 320
■第2章 第1回口頭弁論期日前の運用 325
◎第1節 第1審判決から第1回口頭弁論期日までの手続 326
1 控訴の提起と訴訟記録の送付 326
2 第1回口頭弁論期日の指定 326
◎第2節 第1回口頭弁論期日の充実に向けての方策 326
1 控訴審における早期の審理方針の確定 326
2 控訴理由書の意義、内容及び提出期限 327
3 主任裁判官の役割 328
4 合議の充実 328
5 第1回口頭弁論期日前の進行管理 329
◎第3節 第1回口頭弁論期日における審理 333
1 控訴審における第1回口頭弁論期日 333
2 充実した第1回結審 333
3 続行期日の指定 334
4 心証の開示と不意打ち防止 334
■第3章 続行期日における審理 337
◎第1節 人証の取調べ 338
1 人証取調べの実情 338
2 人証取調べの基準 338
◎第2節 和 解 339
1 和解の実情 339
2 和解における心証開示とその機能 340
■第4章 控訴審の判決書 341
◎第1節 判決書の機能、内容及び様式 342
1 判決書の機能 342
2 判決書の内容 342
3 控訴審の判決書 344
4 事後審的訴訟運営の成果としての控訴審判決書 345
◎第2節 控訴審判決書における第1審判決の引用 347
1 事実摘示と理由説示の引用 347
2 引用判決の長所と欠点 348
3 引用判決の問題点と今後の活用法 348
◎第3節 モデル判決書 351
第1事例【控訴棄却・請求認容判決】 352
第2事例【原判決取消し・差戻し判決】 354
第3事例【訴えの交換的変更後の請求認容判決】 357
第4事例【原判決取消し・請求棄却判決】 363
第5事例【控訴棄却・附帯控訴一部認容判決】 368
第6事例【原告が訴訟脱退した後の引受参加人の請求棄却判決】 381
第7事例【被告側の訴訟承継と原告の請求減縮後の請求認容
判決】 386
■第5章 民事控訴審の審理についての5つの提言 391
◎第1節 民事控訴審のプラクティスの在り方 392
◎第2節 5つの提言 392
1 第1提言(民事控訴審の訴訟運営の基本的視点) 392
2 第2提言(第1回結審の運用の在り方について) 393
3 第3提言(控訴審における人証の取調べの基準と範囲) 393
4 第4提言(控訴審における和解の運用基準) 393
5 第5提言(引用判決の当否を含む控訴審判決書作成の工夫) 394
■第6章 ドイツの民事控訴審の実情 395
◎第1節 ドイツの法曹人口と民事控訴審の実情調査 396
1 ドイツの法曹人口 396
2 民事控訴審の実情調査 396
◎第2節 ドイツの裁判所の事物管轄と上訴制度 396
1 事物管轄 396
2 上訴制度 396
◎第3節 ドイツにおける民訴法の改正の歴史 397
1 1877年法 397
2 1970年以後の改正 397
3 2001年7月27日の改正 398
◎第4節 ドイツの民事控訴審の審理及び手続の概要 403
1 控訴のできる裁判(民訴法511条2項) 403
2 控訴審における年間事件処理件数 403
3 控訴提起期間(民訴法517条) 403
4 控訴理由書の提出(民訴法520条2項) 403
5 事件の振り分け 404
6 控訴棄却決定(民訴法522条2項) 404
7 第1回口頭弁論期日の指定(民訴法523条) 404
8 第1回口頭弁論期日前の主張整理 405
9 単独裁判官による審理(民訴法526、527条) 405
10 期日メモ 405
11 第1回口頭弁論期日の運営 406
12 証拠調べ 406
13 和解勧告の時期 407
14 判決書(民訴法313、313条a第1項) 407
15 判決の言渡し(民訴法310条1項) 408
16 事件処理の終局区分 408
◎第5節 ドイツにおける民訴法改正のまとめ 408
1 ドイツにおける民訴法改正の背景 408
2 我が国の民事控訴審の審理への示唆 408
◎第6節 民訴法522条2項の控訴取下げ勧告決定及び
控訴棄却決定の参考例 409
1 民訴法522条2項の控訴取下げ勧告決定 410
2 民訴法522条2項の控訴棄却決定 412
◎第7節 控訴審判決の参考例 414
◎第8節 主任裁判官が作成する期日メモ(Votum)の参考例 420
◎第9節 ドイツ民訴法中の控訴審に関する主要規定 423
判例索引 433
事項索引 439
▼もっと見る
・具体的事例研究を通して分析し、解決指針を提示。
・控訴審の訴訟運営に関わる実務と理論の架け橋となる書。
![]()