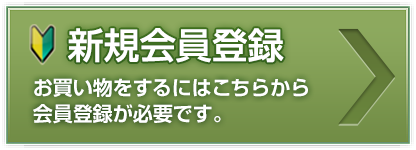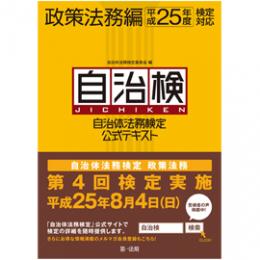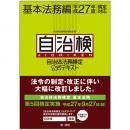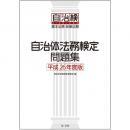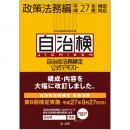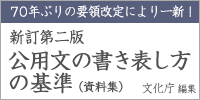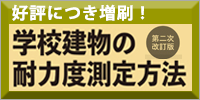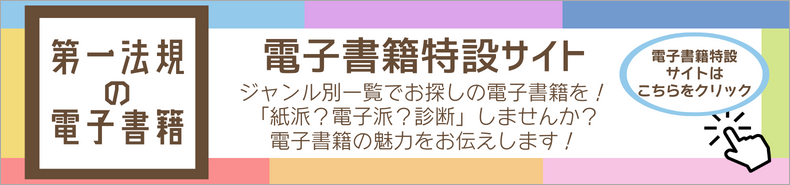第1章 自治体法務とは 1
第1節 自治体法務と政策法務 2
1 自治体の仕事と法治主義 2
2 自治体法務とは 2
3 伝統的法務の問題点 3
4 政策法務とは 4
学習のポイント 5
第2節 地方分権改革と自治体法務 6
1 地方分権改革の理念と戦略 6
2 国(中央政府)及び自治体(地方政府)の役割分担と事務の関係 7
3 地方分権改革と通達制度の廃止 8
4 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大 9
5 国と地方の協議の場に関する法律 14
学習のポイント 17
第3節 人権保障―住民の権利利益をどう守っていくか 18
1 人権保障と統治構造 18
2 裁判所のチェック―違憲審査基準 19
3 判例法理と違憲審査基準 20
4 行政に対する憲法的裁量統制 21
5 人権と条例 22
6 地方自治と住民参加 22
学習のポイント 23
第4節 自治体法務の基本原理 25
1 自治体法務と「法治主義」・「地方自治の本旨」 25
2 自治体法務に必要な諸原則 27
3 国の法務と異なる自治体法務のマネジメント 29
学習のポイント 32
第5節 自治体にかかわる「法」の形式 34
1 自治体に適用される法律とその解釈 34
2 法律以外の国法形式と自治体法務との関係 36
3 条例の類型・内容・制定手続・課題 38
4 規則の類型・内容・制定手続・課題 46
5 その他の自治立法(要綱・協定・計画等) 48
学習のポイント 52
第2章 立法法務の基礎 55
第1節 「立法事実」―なぜ条例が必要なのか 56
1 「立法事実」とは何か 56
2 「立法事実の説明資料」に盛り込む内容 56
3 「立法事実の説明資料」はどのような場面で使用するのか 58
学習のポイント 59
第2節 「行政手法」―地域の課題を公共的に解決するためには 60
1 「行政手法」とは何か 60
2 行政手法を採用する際の留意点 61
3 計画手法の内容・特徴と使い方 63
4 誘導的手法の内容・特徴と使い方 65
5 コミュニケーション手法の内容・特徴と使い方 67
6 規制的手法の内容・特徴と使い方 68
7 実効性確保の手法の内容・特徴と使い方 70
8 その他の行政手法 72
9 行政手法の組合せ 73
学習のポイント 74
第3節 立法の典型的パターンの使い方 76
1 立法のパターンの応用 76
2 規制条例における組合せの選択 79
3 基本条例における行政手法の組合せの選択 83
学習のポイント 86
第4節 規制条例 87
1 規制条例作成のポイント―許可制を題材に 87
2 規制の効果を確保するには 90
3 法律による規制との競合の問題 92
学習のポイント 95
第5節 基本条例 96
1 基本条例作成のポイント―政策フレーム条例を題材に 96
2 基本条例の典型的な要素 97
3 法律との関係の整理 100
4 自治基本条例等 101
学習のポイント 106
第6節 「条例制定権」と「条例で定めなければならない事項」 107
1 条例制定権の範囲(憲法94条に規定する「法律の範囲内」の解釈) 108
2 条例で定めなければならない事項 109
3 規則で定める事項 111
学習のポイント 113
第7節 都道府県条例と市町村条例の関係 11
1 都道府県条例と市町村条例の違い 114
2 都道府県条例と市町村条例が競合する場合の取扱い 116
学習のポイント 120
第8節 法制執務知識 121
1 総則規定 121
2 実体規定 122
3 雑則規定 124
4 罰則規定 125
5 附則規定 127
6 用語の知識 129
学習のポイント 137
第3章 解釈運用法務の基礎 139
第1節 自治事務・法定受託事務の解釈運用 140
1 自治事務・法定受託事務 140
2 解釈手法 143
3 自治体の解釈運用 146
4 処理基準による解釈 148
学習のポイント 151
第2節 行政裁量とその統制 153
1 行政裁量の定義と構造 153
2 司法審査との関係―行政裁量の限界と司法審査の際の統制基準 156
学習のポイント 160
第3節 自治体の解釈、運用に対する国・他自治体の関与 161
1 関与の基本原則 161
2 関与に関する係争処理 162
学習のポイント 167
第4節 違法行為への対応 168
1 行政指導―穏やかな方法による対応 168
2 行政命令―強権発動の第一歩 170
3 告発―刑事処分の第一歩 172
学習のポイント 175
第4章 争訟法務の基礎―行政上の不服申立てと訴訟及びその活用 177
第1節 行政不服審査制度 178
1 行政救済の全体像 178
2 行政不服審査制度の概要 180
3 不服申立ての要件 182
4 行政不服審査制度の仕組みと結果 183
学習のポイント 186
第2節 行政事件訴訟制度 187
1 行政事件訴訟の訴訟パターン 187
2 抗告訴訟の種類 189
3 取消訴訟を起こすために必要な要件とは 192
4 訴訟の重要な手続と判決の効力 194
5 住民訴訟(民衆訴訟)の仕組み 196
学習のポイント 201
第3節 国家賠償制度 203
1 国家賠償法の概要 203
2 「公権力の行使」に関する責任 204
3 「営造物の設置管理」に関する責任 207
学習のポイント 211
第4節 政策訟務とは 212
1 政策訟務の視点 212
学習のポイント 214
第5章 地方自治の制度―地方自治法 215
第1節 自治体の事務 216
1 地方自治法が示す住民の権利とは 216
2 財務に関する基本的なルール 218
3 契約・入札制度 222
4 公の施設の設置・管理に関するルール 225
5 「事務処理特例条例」の意義と効果 227
6 監査制度と住民監査請求の仕組み 229
7 関与 231
学習のポイント 234
第2節 自治体の組織 236
1 普通地方公共団体の組織(長と委員会・委員による多元的な組織) 236
2 特別地方公共団体の組織 240
3 地方議会と長との関係 243
4 附属機関と専門委員の役割 246
5 地方議会の仕組みと役割 248
6 地方議会改革への取組み 252
学習のポイント 260
第6章 行政手続とパブリックコメント 263
第1節 行政手続―行政運営の公正の確保と透明性の向上 264
1 「行政手続制度」の全体像と趣旨 264
2 許認可等の申請に対する処分のルール 266
3 命令、許認可等の取消し等の不利益処分のルール 268
4 指導、勧告等の行政指導のルール 270
5 届出のルール 271
学習のポイント 273
第2節 パブリックコメント制度 274
1 パブリックコメント制度とは 274
2 パブリックコメント制度の意義 274
3 パブリックコメント制度の条例化 275
学習のポイント 279
第7章 情報公開と個人情報保護 281
第1節 自治体における情報公開制度 282
1 情報公開制度の概要 282
2 情報公開の請求権者と対象機関の範囲 286
3 開示・不開示の判断の実際 287
4 情報公開と情報提供―より積極的な情報の提供に向けて 291
学習のポイント 293
第2節 自治体における個人情報保護制度 296
1 個人情報保護の8原則―個人情報保護のルーツ 296
2 個人情報保護の必要性―その理念と実際 296
3 個人情報保護条例における不開示事由とその運用状況―開示・不開示の判断の実際 299
4 事務の外部委託における個人情報漏洩の防止 303
学習のポイント 306
第8章 公共政策と政策法務 307
第1節 公共政策の理論 308
1 公共政策とは何か 308
2 公共政策の構成要素―政策には何が定められているのか 309
3 公共政策のプロセス―政策はどうつくられるか 311
4 公共政策と法―政策と法はどう違うのか 313
5 総合計画と予算―条例との関係はどうあるべきか 314
学習のポイント 316
第2節 行政組織とガバナンス 317
1 行政組織の原理と機能―官僚制の特質 317
2 行政改革とNPM改革 319
3 公共サービスの改革―NPO・ボランティアと自治体 321
4 コミュニティの意味と役割―役所に頼らない地域づくり 323
5 ガバメントからガバナンスへ―「新しい公共」をつくる 325
学習のポイント 328
第3節 政策法務のマネジメント 330
1 政策法務のサイクル―政策の視点で法務の流れを押さえる 330
2 政策法務を担う者たち―政策法務を担うのは誰か 332
3 政策法務の組織戦略―政策法務をどう浸透させるか 335
4 政策法務の人材養成―政策法務に強い職員を育てる 337
5 議会の政策法務―議員は政策法務にどう取り組むか 339
6 住民参加と政策法務―市民は政策法務にどう取り組むか 343
学習のポイント 345
第4節 立法評価のすすめ―すぐれた条例とは何か 346
1 立法評価とは何か 346
2 条例評価の枠組み―条例評価の制度をどう設計するか 347
3 すぐれた条例の条件(1)―条例評価の6つの基準(総論) 350
4 すぐれた条例の条件(2)―基準の内容と当てはめ(各論) 351
5 条例評価の実践―どの時点でどう評価するか 354
学習のポイント 356
参考文献 357
事項索引 363
判例年次索引 373