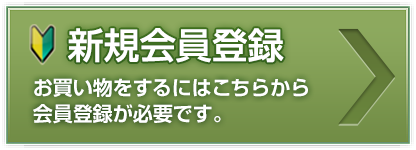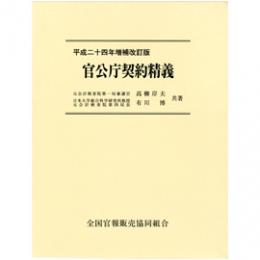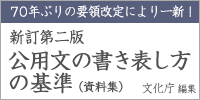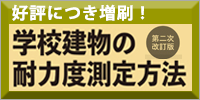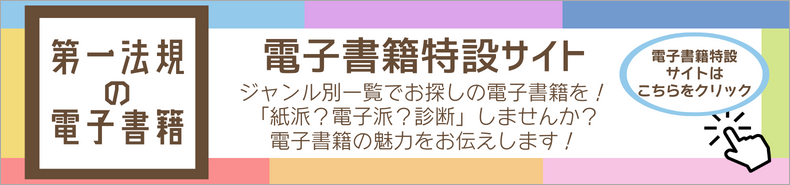▲ ご注文特典希望の方は、注文フォームのメッセージ欄に「ぷにぷに希望」とご入力ください。
▲ ご注文特典希望の方は、注文フォームのメッセージ欄に、キーワード「鉛筆セット」をご入力ください。
官公庁契約精義
平成二十四年増補改訂版
定価
定価
13,200円 (本体:12,000円)
| ISBN | 978-4-915392-99-3 |
| 発刊年月日 | 2012-03-14 |
| 判型 | A5判上製箱入り |
| ページ数 | 1552 |
| 巻数/略称 | / 契約精義24 |
| 商品コード | 028167 |
商品概要
総務省、独立行政法人、国立大学法人の契約監視委員を務める有川博氏による改訂。独立行政法人を含む最新の契約内容を網羅した他に類のない、唯一の官公庁契約実務詳説である。
目次
商品の特色
【前回版からの増補改訂概要】
・公共調達の改革、特に随意契約の新たな見直しの内容
・一者入札の問題とその発生原因の分析
・独立行政法人と国立大学法人の契約に係るルールと問題点
・低入札価格調査に係る特別重点調査の現状と問題点
・官製談合防止法の運用実例と独占禁止法の改正動向
今回はさらに次のような部分を中心に、新たに記述又は加筆が行われました。
1.東日本震災被災地域に係る公共調達面での配慮事項について、中小企業施策、地域施策等関係の箇所に記述
2.グリーン購入法関係のデータを新しくするとともに、グリーン契約法(環境配慮契約法)についても新たに節を立て解説
3.「独立行政法人の契約状況の点検・見直し」に基づく最新の見直し等の状況を加筆
4.国立大学法人の少額随契の問題について、その後の状況を踏まえて加筆
5.平成19年度以降の随意契約の見直し状況のフォローアップについて記述
6.入札適正化指針の平成23年の大改正を踏まえ、各改正項目を新旧対照の形で記述
7.公共工事標準請負契約約款について、改正に即して引用条項や資料を新しいものに改めるとともに、必要な解説を加筆
8.総合評価落札方式の見直しの動向について、新たに節を立てて解説
9.PFI法の平成23年の改正内容を盛り込むとともに、PFI事業に係る平成23年11月の会計検査報告についても解説
10.「公共サービス改革法と市場化テスト」の章を新設するとともに、「公共サービス基本法」についても節を立てて解説
11.「情報システムと調達の問題」の章に、新たに「情報システムに係る政府調達の基本方針」の節を立てて加筆し、この中で、情報システム調達に係る平成23年11月の会計検査報告についても解説