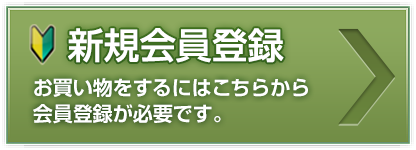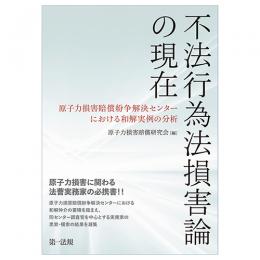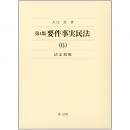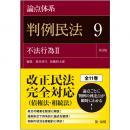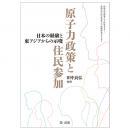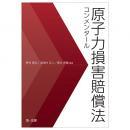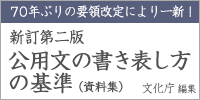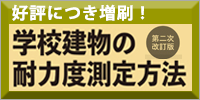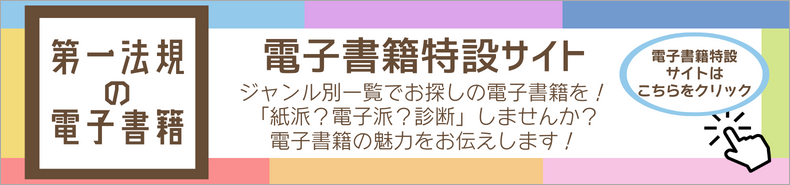不法行為法損害論の現在~原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解実例の分析~
原子力損害賠償紛争解決センターの調査官を中心とする同センターの法曹実務家による、原子力損害賠償の損害論についての思索と模索の結果を凝集した唯一の書籍!
定価
定価
9,790円 (本体:8,900円)
![]()
編著者名
原子力損害賠償研究会 編
| ISBN | 978-4-474-07896-3 |
| 発刊年月日 | 2023-12-19 |
| 判型 | A5判/C2032 |
| ページ数 | 672 |
| 巻数/略称 | / 不法行為損害 |
| 商品コード | 078964 |
商品概要
原子力損害賠償紛争解決センターに所属する法曹実務家が、2011年3月に発生した福島第一、第二原子力発電所の事故発生から12年の間に行ってきた数多くの原子力損害の賠償の和解仲介の蓄積を踏まえ、その実務を紹介し、さらに、その基礎にある理論や基本的な考え方を詳説した解説書!
目次
推薦の辞
はしがき
執筆者一覧
用語例
裁判例出典略語
第1部 損害論
第1章 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う原子力損害賠償請求権についての基本的考察~原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続における実務も踏まえて~
1 原子力損害賠償請求権についての基本的考察
⑴ はじめに
⑵ 民法の不法行為に基づく損害賠償請求権について
ア 目的・要件等
イ 損 害
ア 損害の捉え方(差額説)
イ 損害項目の分類・整理等
ウ 損害額の調整
ア 過失相殺
イ 素因減額
ウ 損益相殺及び損益相殺的調整
エ 消滅時効
⑶ 原子力損害賠償請求権の特殊性について
ア 原子力損害について
イ 原子力損害賠償制度の特殊性(無過失責任、無限責任、責任集中、損害賠償措置額等)
ウ 消滅時効の特例等
エ 紛争解決のための特殊性(原子力損害賠償紛争審査会及びそれに伴う制度等)
⑷ 原子力損害賠償における個別損害項目についての概要
ア 積極損害
ア 避難等に係る損害
イ 財物損害
イ 精神的損害
ア 生命・身体損害としての入通院慰謝料、死亡慰謝料等
イ 本件事故の避難等による日常生活阻害慰謝料(慰謝料の増額も含む。)
ウ 過酷避難状況による精神的損害
エ 生活基盤喪失・変容による精神的損害
オ 相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害
カ その他の慰謝料
ウ 消極損害
ア 営業損害
イ 就労不能損害
エ その他
2 原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続における実務を踏まえた原子力損害賠償請求権の実現について
⑴ ADRセンターにおける仲介委員が実施する和解仲介手続
⑵ 因果関係の判断と影響割合という概念について
ア 因果関係の判断について
イ 影響割合(寄与度)という概念について
⑶ 弁護士費用について
⑷ 遅延損害金について
⑸ 和解仲介手続と清算条項について
3 損害拡大防止義務(損害軽減義務)
⑴ はじめに
⑵ 損害軽減義務に関する従前の議論
ア 学 説
ア 過失相殺制度との関係で論じるもの
イ 過失相殺以外の場面において論じるもの
イ 判例(最二小判平成21・1・19民集63巻1号97頁〔28150152〕)
ア 事案の概要
イ 判示内容
ウ 本項との関係
ウ 債権法改正
ア 議論の経緯
イ 本項との関係
⑶ 中間指針策定における議論の概観、整理
ア 中間指針の定め
イ 審査会の議論
ウ 中間指針についての考察
ア 本件事故の被害者に損害軽減義務を認めることについて
イ 中間指針が定める要件について
ウ 考慮要素
エ 損害軽減義務の不法行為法上の位置付け
オ 効 果
⑷ 事故後の下級審判例
ア 大阪地判平成27・9・16判タ1423号279頁〔28233548〕
イ 東京地判平成29・10・11平成24年(ワ)35723号公刊物未登載〔28254964〕
ウ 仙台高判令和元・10・30平成31年(ネ)8号公刊物未登載〔28292894〕
第2章 各 論
1 避難等に係る損害
⑴ はじめに
⑵ 中間指針等の整理
ア 避難指示等対象区域
ア 中間指針等に基づく損害項目(積極損害)の整理
イ 賠償対象期間(避難費用について)
イ 自主的避難等対象区域
ア 中間指針等に基づく損害項目(積極損害)の整理
イ 自主的避難の定義(類型)
ウ 対象区域及び対象者
エ 損害項目
オ 賠償対象期間
カ 総括基準
⑶ 当センターにおける和解仲介手続
ア はじめに
イ 避難指示等対象区域
ア 生活費の増加費用
イ 賠償対象期間
ウ 住居確保損害の賠償を受ける場合について
エ 損害の認定方法
ウ 自主的避難等対象区域
ア はじめに
イ 避難実行者の生活費増加費用等
ウ 滞在者の生活費増加費用等
エ 賠償対象期間
オ 移動行為の避難該当性
カ 除染及びその関連費用(自主除染)
キ 区域外からの避難に対する賠償
ク 損害の認定方法
ケ 損害の算定方法及び既払金控除の問題
2 財物損害
⑴ 総 論
ア はじめに
ア 本件事故の特殊性
イ 本項の検討範囲
イ 財物損害に関する民法の規定、従来の学説
ア 物の滅失の場合の「損害」
イ 物の損傷の場合の「損害」
ウ 物の不法占有の場合の「損害」
ウ 本件事故前の原発事故、大規模災害における財物損害に関する裁判例
⑵ 各 論
ア 個人住宅
ア 財物損害
イ 移住加算・住居確保損害
イ 農 地
ア 財物損害における農業の特徴
イ 中間指針等
ウ 損害類型等
エ 審査会での議論
オ ADRセンターでの取扱い
カ 本件事故後の裁判例
ウ 事業用不動産
ア 事業用不動産の特徴
イ 中間指針等の賠償基準
エ 事業用動産
ア 従来の裁判例
イ 学説の展開
ウ 中間指針等の定めとその背景
エ ADRセンターの取扱い
オ 本件事故後の裁判例
オ ケーススタディ
ア 〇〇町の土地(宅地)建物について
イ 住居確保損害(第四次追補)相当部分について
ウ 宅地以外の土地(農地等)について
3 精神的損害
⑴ 生命・身体的損害としての精神的損害(後遺障害・死亡慰謝料及び入通院慰謝料)
ア はじめに
イ 基本概念と判例
ア 相当因果関係
イ 相当因果関係の立証困難に関する学説、裁判例
ウ 被害者の素因
ウ 生命・身体的損害としての傷害(入通院)慰謝料、後遺障害・死亡慰謝料の基準額
ア 赤い本の死亡慰謝料基準額について
イ 「相当程度の可能性」を認めた事案
ウ 慰謝料の増減事由
エ 本件事故に関連する死亡事案についての裁判例
ア 本件事故後の避難から近接した時期の病死に関するもの
イ 本件事故後の避難中の自死事案に関するもの
オ 中間指針
カ センターのADRにおける和解実務
ア はじめに
イ 代表的な死亡事案の類型
ウ 審理方法
エ ADRにおける因果関係判断
オ 影響割合について
カ 死亡慰謝料の基準額について
⑵ 避難等対象者該当性(単身赴任者・学生)
ア はじめに
イ 中間指針における精神的損害及び避難等対象者の定義に関する規定及びその解釈について
ア 両規定の内容について
イ 中間指針から理解される「避難等対象者」という要件の意味について
ウ 精神的損害の特質及びADRの役割から考える避難等対象者という要件の意味について
ウ ADRにおける和解実務のあり方について
ア 学生や単身赴任者のケースについて
イ 区域外からの転入予定者のケースについて
ウ ADRにおける考慮要素について
エ ケーススタディ
⑶ 滞在者の精神的損害
ア はじめに
イ 問題の所在
ア 福島県南相馬市における緊急時避難準備区域の設定・解除に至る経緯
イ 中間指針等の規定について
ウ 避難者と滞在者等との賠償格差
ウ 原町区集団事件の申立て
ア 和解案提示に至る経緯
イ 本件における和解案
ウ 東京電力の対応
エ 本件集団事件の解決を踏まえた総括基準の策定、東電の賠償基準の遷移、裁判例
ア 総括基準(旧緊急時避難準備区域の滞在者慰謝料等について)の策定
イ 東京電力の賠償基準の変遷
ウ 中間指針
エ 裁判例について
オ 終わりに
カ ケーススタディ
ア 避難者の精神的損害について
イ 滞在者、避難後帰還者の慰謝料請求の法的構成
ウ 滞在者慰謝料の法的構成(総括基準か東電基準か)
エ 滞在者慰謝料の増額について
⑷ 緊急時避難準備区域における避難継続慰謝料
ア 問題の所在
ア 緊急時避難準備区域とその特徴
イ 一律の避難終了時期設定の必要性と問題点
イ 中間指針第二次追補の「相当期間」
ア 緊急時避難準備区域について
イ 中間指針第二次追補の背景と解釈
ウ センターでの和解の実例(類型による分類)
ア 医療上の必要性
イ 就学上の必要性
ウ その他
エ ケーススタディ
ア ケース1の⑴について
イ ケース1の⑵について
ウ ケース2について
⑸ 日常生活阻害慰謝料の増額事由
ア はじめに
イ 総括基準(精神的損害の増額事由等について)
ウ 総括基準を踏まえたセンターにおける増額割合についての運用
エ 第五次追補
オ 第五次追補がセンターにおける運用に与える影響
⑹ その他・遺体捜索慰謝料
ア はじめに
イ 「遺体捜索慰謝料」に関する中間指針等及び裁判例の現状
ア 審査会での議論
イ 中間指針等
ウ 裁判例
ウ センターのADRにおける和解実務
ア 平成24年遺体捜索集団案件(公表事例698、和解案提示理由書20)
イ 平成26年遺体捜索案件(公表事例1061)
ウ 小 括
エ ケーススタディ
ア 居住地及び遺体発見時期の問題
イ 賠償が認められる者の範囲
4 営業損害
⑴ 風評被害
ア はじめに
イ 原子力事故における風評被害についての先行裁判例等
ア 先行裁判例
イ ジェー・シー・オー臨界事故における「中間的な確認事項(営業損害に対する考え方」及び最終報告書
ウ 中間指針における風評被害に関する規定
ア 中間指針における風評被害に関する規定の概要
イ 先行裁判例等と中間指針の関係
エ 本件事故による風評被害に関する裁判例
ア 裁判例の概要
イ 裁判例における風評被害の考慮要素(ゴルフ場の事案を中心として)
オ センターにおける和解実務
ア センターにおける風評被害申立て案件の審理の状況
イ 公表事例からみる和解内容の全般的な特徴
ウ 業種ごとの風評被害の認定における考慮要素・和解内容
エ まとめ
カ ケーススタディ
ア ケース1
イ ケース2
⑵ 間接損害
ア はじめに
イ 間接損害に関する従来の議論
ア 間接損害の類型
ウ 中間指針における間接損害の規定及び同指針策定までの経緯
ア 中間指針の規定とその特徴
イ 審査会における間接被害に関する議論の経過
ウ 中間指針と43年判決との整合性についての考察
エ ADRにおける和解実務のあり方と裁判例の検討
ア 裁判例の検討
イ ADRにおける和解実務
ウ 考 察
オ ケーススタディ
⑶ 営業損害(逸失利益)の算定方法
ア 損害額の算定
ア はじめに
イ 損害額算定方式の概要
ウ 具体的な損害額の算定方法
エ 休業している場合に生じる問題点
オ センターでの取扱い
カ ケーススタディ
イ 寄与度(影響割合)について
ア はじめに
イ 審査会での議論及び中間指針等
ウ 割合的解決に関する裁判例及び学説の状況について
エ ADRにおける和解実務
オ 本件事故に関する裁判例の検討
カ まとめ
キ ケーススタディ
⑷ 農林業の風評被害
ア 農林業の被害について
ア 農林業に対する原発事故の影響(概要)
イ 農林業に対する原発事故の影響の特殊性
イ 中間指針の規定
ア 中間指針の規定について
イ 中間指針第三次追補の規定について
ウ ADRにおける和解実務のあり方・取扱い
ア 逸失利益について
イ 追加的費用について(積極的損害)
エ 農林業の風評被害の実情
ア 客観的な資料収集の困難性
イ 被害の広範性・継続性及び生産再開の困難性
オ ケーススタディ
ア 相当因果関係について
イ 損害の継続期間について
ウ その他
別 表
5 就労不能損害
⑴ 就労不能損害の基本概念
ア 就労不能損害とは
イ 中間指針の考え方
ア 中間指針(抜粋)
イ 中間指針の考え方
⑵ 検討・考察
ア 就労不能損害の要素
ア 減収
イ 相当因果関係
イ 避難の長期化に伴う問題点
ア 本件事故前に従事していた就労の機会を事故がなくとも失っていた場合
イ 申立人側の事情による就労不能
ウ 就労不能損害の終期
ア 終期の考え方
イ 「被害者が従来と同じ又は同等の就労活動を営むことが可能となった日」の到来について
ウ 被害者側の損害回避・減少に係る措置について
エ 割合的認定
オ 特別の努力
⑶ ケーススタディ
ア 減収について
イ 特別の努力
ウ 就労不能損害の終期
エ 退職金
6 中間指針第五次追補の概説
⑴ 過酷避難状況による精神的損害(第五次追補第2の1)
ア 追補の経緯等
イ 第五次追補第2の1の規定
ウ 対象区域・対象者
ア 対象区域
イ 対象者
エ 損害額の目安
ア 具体的な損害賠償の方法及び金額
イ 過酷避難状況による精神的損害の増額
⑵ 避難費用、日常生活阻害慰謝料及び生活基盤喪失・変容による精神的損害(第五次追補第2の2)
ア 追補の経緯等
イ 第五次追補第2の2の規定
ウ 生活基盤喪失・変容による精神的損害
ア 生活基盤喪失・変容による精神的損害の内容
イ 実務上の問題点
エ 避難費用及び日常生活阻害慰謝料
ア 第五次追補の概要
イ 実務への影響等
⑶ 相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害(第五次追補第2の3)
ア 追補の経緯等
イ 第五次追補第2の3の規定
ウ 相当線量地域健康不安に基礎を置く精神的損害の内容、対象者等
ア 精神的損害の内容
イ 対象区域及び対象者
ウ 賠償額と算定方法
エ 対象期間
オ 過酷避難状況による精神的損害との関係
⑷ 精神的損害の増額事由(第五次追補第2の4)
ア 追補の経緯等
イ 総括基準(精神的損害の増額事由等について)
ウ 第五次追補第2の4の規定
ア 精神的損害の増額事由の要件と増額の目安額
イ 各事由について
ウ 自主的避難等対象区域について(備考2)
⑸ 自主的避難等に係る損害について(第五次追補第3)
ア 追補の経緯等
イ 第五次追補第3の規定
ウ 中間指針追補、第二次追補の概要
ア 中間指針追補(平成23年12月6日策定)
イ 第二次追補(平成24年3月16日策定)
エ 第五次追補における見直しの概要
ア 中間指針追補・中間指針第二次追補の基本的な枠組みの維持
イ 妊婦・子供以外の賠償期間や賠償額の見直し
ウ 精神的損害の増額事由の尊重(第五次追補第2の4の備考2)
エ その他
第2部 ADRの手続と審理
第1章 草創期から安定期までの原発ADRセンターの運営
野山 宏
1 揺籃期・平成23年9月~同年11月
⑴ 着任当初
⑵ 寄合所帯・混成部隊
⑶ 権限の委任など組織運営体制の整備
⑷ 受付開始当初2か月ほどの状況
⑸ 初期の調査官の執務
⑹ 初期の仲介委員の執務
⑺ 初期の和解成立状況
⑻ 申立書類の印象など
2 破綻クライシス期・平成23年12月~平成24年8月
⑴ 破綻クライシスの発生
⑵ 初 動
⑶ 応急措置1―調査事務の簡素化
⑷ 応急措置2―審理の簡素化
ア 単独制仲介委員の導入・単独制の原則化
イ 書面審理の活用(口頭審理の限定的運用)
ウ 和解案提示理由書の原則不作成
エ 民事訴訟法不適用の再確認
オ 応急措置の効果
⑸ 抜本的措置
⑹ 応急措置等の効果
3 クライシス脱却期・平成24年9月~平成25年1月
⑴ 調査官の増員
⑵ 事務所移転と執務場所のオープンスペース化
⑶ 調査官の8係再編成と新旧調査官の一体感の涵養
⑷ 室長補佐の増員
⑸ 仲介委員との一体感の涵養など
⑹ 審理上の工夫
⑺ 破綻クライシスからの脱却
4 安定期・平成25年2月~平成26年3月
⑴ 事件処理状況
⑵ 調査官の12係再編成と自主的避難係の第2事務所移転
⑶ 室長補佐のさらなる増強
⑷ 調査官の増強
5 福島県での説明会など
6 日弁連での説明会
7 報道機関対応
8 組織概要―和解仲介室を中心に
⑴ 統制のとれた任務遂行
⑵ 東京事務所
⑶ 福島事務所
第2章 集団事件の審理
1 はじめに
2 集団事件の類型
⑴ 本件事故前の居住地が互いに近接している住民からの申立て
⑵ 避難先が互いに近接している住民からの申立て
⑶ 申立人代理人の有無
⑷ 請求内容による分類
ア 申立人間に共通する一つの損害の賠償を求める類型
イ 申立人ごとに各種損害の賠償を請求する類型
3 集団事件の審理方法
⑴ はじめに
⑵ 申立段階の工夫
⑶ 審理及び手続進行の工夫
ア チャンピオン方式
イ 審理方針の共有
ウ 電子データの活用(特に複数論点型の場合)
エ 代表者の陳述、陳述書、現地視察の活用
オ 積極的釈明・アンケートの活用(特に本人申立ての場合)
カ 証拠方法の共通化
キ 一部和解の活用
⑷ 審理終了後のフォロー
4 センター公表事例にみる具体例
⑴ 公表事例331(代理人:有、請求損害項目:複数)
⑵ 公表事例698(代理人:有、請求損害項目:単一)
⑶ 公表事例907(代理人:無、請求損害項目:単一)
⑷ 公表事例910(代理人:有、請求損害項目:複数)
⑸ 公表事例923(代理人:有、請求損害項目:単一)
⑹ 公表事例960(代理人:有、請求損害項目:複数)
⑺ 公表事例985(代理人:有、請求損害項目:複数)
⑻ 公表事例1028(代理人:有、請求損害項目:単一)
⑼ 公表事例1192(代理人:無、請求損害項目:複数)
⑽ 公表事例1291(代理人:有、請求損害項目:単一)
⑾ 公表事例1404(代理人:無、請求損害項目:単一(ただし申立時))
⑿ 和解案提示理由書(成立に至らなかった事例)番号1
⒀ 和解案提示理由書(成立に至らなかった事例)番号2から5まで
⒁ 和解案提示理由書(成立に至らなかった事例)番号6、7及び10
別表1
別表2
第3章 地方公共団体の審理について
1 総 論
⑴ 地方公共団体の損害賠償請求の概要
ア 地方公共団体の損害賠償請求における基本的事項及びその特徴
ア 申立人たる地方公共団体について
イ 請求項目、請求対象期間等について
イ ADRの申立てから終了までの流れ
ア 申立書の提出
イ 答弁書の提出
ウ パネルでの審理
エ 和解案骨子の送付
オ 和解案提示
ウ ADRにおける審理の内容
ア 本件事故と事業(支出)の関連性
イ 追加性
ウ 事業(支出)の必要性
エ 事業(支出)内容の相当性
⑵ 中間指針等の定め
ア 中間指針の定め
ア 中間指針第10の2 地方公共団体等の財産的損害等
イ 中間指針第二次追補第4 除染等に係る損害について
ウ 中間指針第3の10 財物価値の喪失又は減少等
イ 審査会の共通見解
ア 地方公共団体の税収減について
イ 地方公共団体における不動産の賠償について
ウ 地方公共団体におけるインフラや山林の取扱いについて
2 各 論
⑴ 測定経費
ア 測定経費請求の概要
ア 測定経費請求の根拠
イ 放射線量・放射性物質濃度の測定の概要
イ 測定経費請求の具体例
⑵ 機器購入費
ア 機器購入費請求の概要
ア 機器購入費用請求の根拠
イ 測定機器の種類
ウ 測定機器の利用方法
エ 機器購入費請求の特徴
オ 機器購入費請求の審理
イ 機器購入費請求の具体例
⑶ 除染経費
ア 除染経費請求の概要
ア 除染経費請求の根拠
イ 除染経費請求の審理
イ 除染経費請求の具体例
⑷ 広報経費
ア 広報経費請求の概要
ア 広報経費請求の根拠
イ 広報経費請求の内容
ウ 広報経費請求の審理
イ 広報経費請求の具体例
⑸ 旅費交通費
ア 旅費交通費請求の概要
ア 旅費交通費請求の根拠
イ 旅費交通費請求の内容
ウ 旅費交通費請求の審理
イ 旅費交通費請求の具体例
⑹ 人件費
ア 人件費請求の概要
ア 人件費請求の根拠
イ 人件費請求の特徴
ウ 人件費請求の審理
エ 人件費(正規職員の時間外人件費)請求の審理方式
オ 人件費(臨時職員の人件費)請求の審理方式
イ 人件費請求の具体例
⑺ その他の損害
ア 民間事業者と同様の立場で行う事業に関する損害
ア 概 要
イ 民間事業者と同様の立場で行う事業に関する損害請求の具体例
イ 財物損害
ア 概 要
イ 財物損害請求の具体例
ウ 税収減
第3部 座談会
大谷禎男・鈴木五十三・山本和彦・古谷恭一郎
1 座談会の趣旨及び自己紹介
2 センター開所及びその直後(平成23年9月~平成24年2月)
⑴ センター開所前後
ア 開所前夜
イ センターの組織のつくり方・その運営(調査官制度について)
ウ 開所直後
⑵ 総括基準
ア 総括基準の必要性
イ 総括基準の具体例
⑶ 清算条項
3 急増する事件とその対応(平成24年3月~8月)
⑴ 事件状況と事件増対策
⑵ 審理促進策
⑶ 新たに制度設計をする場合に留意すべきこと
⑷ 激動の1年を振り返って
4 センター開所から1年経過後(平成24年9月~)
⑴ 訴訟との関係
⑵ 審理期間
⑶ センター限りとする情報の扱い
5 終わりに
事項索引
判例索引
商品の特色
〇原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)は、開設から12年が経過し、この間に2万8000件を超える案件(事件)を処理し、うち2万2000件を超える事件について和解成立という実績を有する同センター所属の法曹実務家が執筆。
〇ADRセンターで蓄積された知見やノウハウは、原子力損害賠償案件を扱う法曹実務家にとって非常に有益なものとなり、多くの被害者に対するよりきめの細かい賠償の実現につなげることができる。
〇2022年12月に中間指針第五次追補が策定され、被害者の精神的損害について、賠償の対象となる損害項目、賠償期間などを全般的に見直す内容になっていて、被害者の救済にとって重要な意味を有するものである。本書においては必要な範囲で第五次追補について説明、言及している。