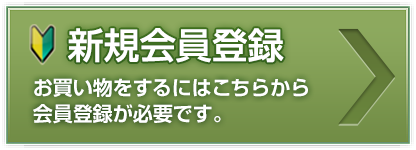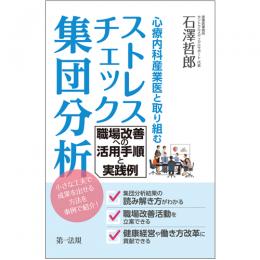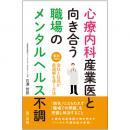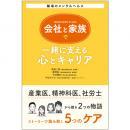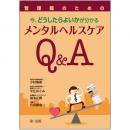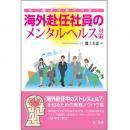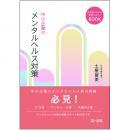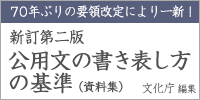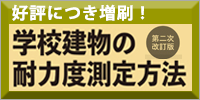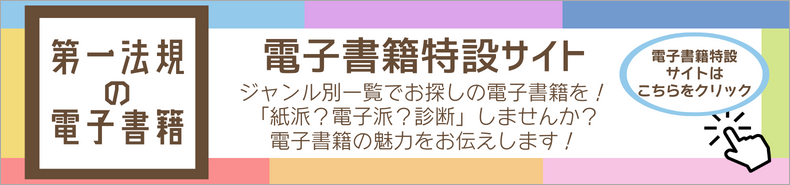労務担当者がストレスチェック集団分析結果を積極活用して、職場改善に向けて次の一手を打つための実務解説書
2,530円 (本体:2,300円)

| ISBN |
978-4-474-06720-2 |
| 発刊年月日 |
2020-03-12
|
| 判型 |
四六判 / C2034 |
| ページ数 |
264 |
| 巻数/略称 |
/ 産業医ストレス |
| 商品コード |
067207
|
ストレスチェック集団分析結果を活用して職場改善を実現する方法を、心療内科産業医が解説。専門スタッフが十分にいない企業等でも、労務担当者等が主体となって職場改善に取り組み、健康経営や働き方改革に貢献する方法がわかる。
◆第1章 ストレスチェックとは
・ストレスチェック制度の成り立ち
産業衛生活動の歴史/集団分析の位置付け
・ストレスチェック制度の流れ
導入前の準備/ストレスチェックの実施/高ストレス者面接の実施/ストレスチェック終了後に行うこと
・集団分析の活用
集団分析の意義/職場改善活動の重要性
◆第2章 集団分析の結果を読み解く
・職業性ストレスモデルについて
ストレスとメンタルヘルスの関係/ストレスの3つの要因/ストレス反応を減らすために
・職業性ストレス簡易調査票に準拠した集団分析の読み方
職業性ストレス簡易調査票の内容とストレス得点/仕事のストレス判定図とは/仕事のストレス判定図以外の情報の活用法
・職業性ストレス簡易調査票以外を用いた集団分析
職業性ストレス簡易調査票の限界/ワーク・エンゲイジメントとは
○コラム1 プレゼンティーズムとアブセンティーズム
◆第3章 職場改善活動の進め方
・自社の立ち位置を確認する
【仕事の量的負担】に問題がある場合/【仕事のコントロール】に問題がある場合/「支援」の強化が必要な場合
○コラム2 職場のハラスメント問題
・従業員の属性による違いを把握する
性別で分ける/年代別に分ける/雇用形態別に分ける
・部署や事業所による違いを確認する
営業部門/間接部門/地方事業所/工場や工事現場/接客業務を行う部門・事業所/システムエンジニアなどの客先常駐業務
・過去データとの変化を確認する
職場改善のPDCAサイクル/職場の環境変化があった場合の対応
・高ストレス者と集団分析
・自社の保有する従業員の健康関連情報を活用する
集団分析と労働時間/集団分析と健診結果
・より詳しい調査票を活用する
○コラム3 ストレス耐性と集団分析
◆第4章 職場改善活動の展開
・展開する上での注意点
・職場改善活動の3つの進め方
経営者主導型/管理職主導型/従業員参加型
・職場改善活動後の評価と次年度の方針決定
・法的な注意事項
個人情報保護との関係/不利益取り扱い禁止の問題/職場改善活動未実施の法的リスク
◆第5章 ケーススタディ
・ケーススタディに取り組むにあたって
・ケース1 若手従業員に高ストレス者が多いH社の事例 ~管理職中心の職場改善活動~
一部の人だけでは?/若者のメンタルが弱いだけ?/コミュニケーションが下手なのでは?/仕事に夢を見すぎでは?/仕事のやりがいがわかっていない
・ケース2 中間管理職のストレス度が高いK社の事例 ~経営者中心の職場改善活動~
ストレス度が高い=病気?/以前より労働時間は減っているはずでは?/プライベートの問題も関係しているのでは?/部署による違いは?/出世への意識変化やマネジメント能力とのミスマッチは?
・ケース3 特定の職場に問題があったN社の事例 ~衛生委員会で考える職場改善活動~
以前から気になっていたが…/他の部署との働き方の違いは?/管理職のマネジメントの問題は?パワハラでは?/誰に、どこまで伝えれば?/会社全体の改善施策につなげるには?
・ケース4 労働時間や生活習慣との関連を検討したP社の事例 ~ボトムアップの職場改善活動~
忙しい工事現場では休みが取れない/環境変化が原因では?/人事データと紐付けて分析できる?/ストレスと体重の関係は?/職場改善活動の具体的な進め方は?
・ケース5 ワーク・エンゲイジメントやストレス耐性の指標を活用したU社の事例 ~ポジティブ指標を用いた職場改善活動~
ワーク・エンゲイジメント以前の問題があるのでは?/どこから手をつければいい?/もっと細かく特徴を知りたい/ストレスが少ないのは良いことでは?/ストレス耐性が低いのは個人の問題?
▼もっと見る
○ストレスチェック後に放置されがちな集団分析結果の「読み解き方」がわかる
○メンタルヘルス不調や長時間労働など様々な問題の解決に向けて、自社で実現可能な「職場改善活動」を立案できる
○職場改善活動を通じて「健康経営」や「働き方改革」に貢献できる
○具体的な職場改善活動の進め方について、「管理職」「衛生委員会」など活動実施主体のバリエーション別に5つの事例を提示、それぞれの立場により陥りがちな思考と実現可能な職場改善活動のヒントを詳しく解説
○心療内科専門医、総合内科専門医、医学博士、法務博士(司法試験合格)等の資格を有する著者が、メンタルヘルス分野の専門性をいかし、産業医としての豊富な実務経験をベースに執筆
![]()